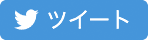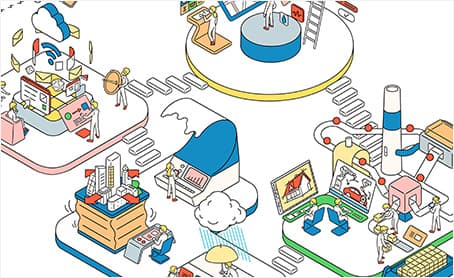講演レポート
「人才」を育む知識創造企業を目指して
構造計画研究所は事業活動の基盤となる人・組織づくりにも大学・研究機関から生まれた学問知を取り入れています。当社の人事制度、企業理念づくりにご協力をいただいた多摩大学大学院徳岡教授に、私たちの企業文化への評価やさらなる価値創造への期待についてお話しいただきました。

- 徳岡 晃一郎 氏
-
東京大学教養学部を卒業後、日産自動車人事部、欧州日産を経て、1999年より米フライシュマン・ヒラード日本法人のSVP(シニアバイスプレジデント)。2006年より多摩大学大学院教授、2014年より同大学院研究科長。2021年4月より学長特別補佐を務める。2017年に株式会社ライフシフトを創業し、ライフシフト大学を開講している。
思いを育むマネジメントで知識創造企業へ
情報社会から知識社会への移行に伴い、企業にとっての人の位置づけが、経営のリソースとして扱う“人材”から“人財”へ、更には、個人のタレントに着目する“人才”へと変化してきています。企業が知識創造企業(Knowledge-creating company)として持続的に成長していくには、事業の戦略やプロセスもさることながら、多様な人才を育成、モチベートし、評価するための企業の知識創造基盤をしっかり構築することが重要となります。私が関わった構造計画研究所の人事制度では、従来の人事評価の主流だった成果主義の考え方だけでなく、MBO(目標によるマネジメント:Management By Objective)やMBB(思いのマネジメント:Management By Belief)を取り入れました。人は誰しも仕事や人生に対する強い思いを持っています。MBBでは、自分の思いをミッション・ビジョンとして言語化し、上司とのコミュケーションを通して会社や社会が求める方向性とすり合わせることで、一人ひとりの思いの高質化を図ります。また、仕事以外に自分が好きなことを見つけて、あたかも仕事のようにコミットする「シャドーワーク」を推奨することで、思いを育むことを後押しできます。これらは先進的で個人の成長への欲求がカギになる取り組みですが、私は所員へのインタビューを通して、「構造計画研究所にはMBBを実践できる土壌がある」と確信していました。
イノベーションを起こす集団としての可能性

デジタル化、グローバル化が加速する一方で、地球環境保全をはじめとする様々な社会課題が顕在化してきている不透明な時代にあっては、イノベーションを起こし続けることが欠かせません。そのためには時代の曲がり角にあって、社会課題としっかりと向き合いながら、「未来はどういう方向へ向かうべきか」を大きな視野から議論することが大切です。すぐに答えは出せなくとも、みんなで議論をして、どんな未来を目指していくかを決めていく。そして未来へのストーリーを自らの言葉で語ることにより、世の中の共感を獲得し多くのパートナーやクライアントを巻き込み、イノベーションを起こすことが可能となります。構造計画研究所は、それができる企業だと感じています。「シャドーワーク」や「学会への参加」「大学、研究機関とのコラボレーション」などが推奨される環境下で、それぞれの思いを育んだ人才の集団は、いろいろな視点から丁寧な議論をし、地道に試行錯誤することを得意とすると考えるからです。さらにアカデミックな世界とのつながりを通して、ビジネスの世界にはない、短期的な成果に囚われない価値観や時間軸に触れられることも、大きな強みになると思います。
ユニークなポジションをいかして世界に貢献を
構造計画研究所は、未来へのストーリーを語るにふさわしいユニークなポジションにある企業といえます。未来を予見することは「デザイン」、未来を構築することは「エンジニアリング」と表現できますから、未来へのストーリーを語ることは、構造計画研究所が企業理念に謳う「デザイン&エンジニアリング企業」と一致しています。
私は、構造計画研究所の企業理念づくりにも協力させていただきましたが、Thought(社会と共に目指す未来像・方向性)として策定した「Innovating for a Wise Future」は、同社の社会に対するメッセージとして多くのステークホルダーの共感を得るものだと思っています。
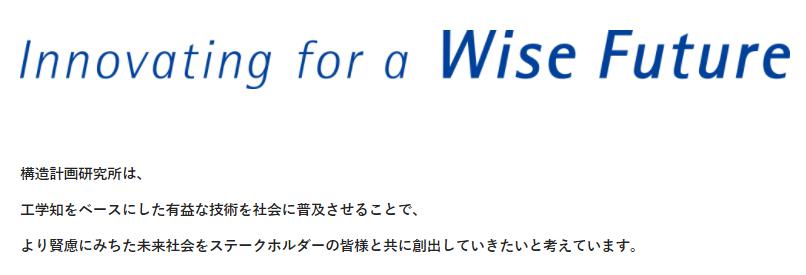
ただし、コロナ禍によってニューノーマル(新常態)が模索されるなか、求められるInnovationやWise(賢慮)やFutureの再定義が必要になっています。その際、重要となるのがグローバルな視野に立つことです。国家や企業の存在意義や価値観が揺らぐ中で、今度こそ、日本社会や企業がグローバルに勝負できる戦闘力を持つことが不可欠になります。そこで、構造計画研究所を支える皆さんには、「自分たちの技術やサービスでいかに国際社会に貢献していくか」「国際社会における日本のプレゼンスを高めるソリューションをいかに創出するか」といったスケールの大きなストーリーを描いて、その実現に挑戦することを期待しています。