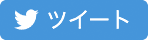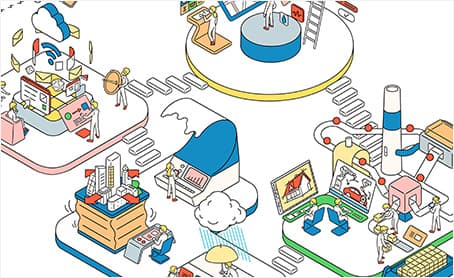講演レポート
サステナブルな建築・都市の実現に向けて
構造計画研究所は、国立大学法人東京大学生産技術研究所と社会連携研究部門「建築・都市サイバー・フィジカル・アーキテクチャ学」を2020年4月に設置し、野城 智也教授との共同研究を進めています。本記事では野城教授にサステナブルな建築・都市の実現に向けた取り組みについて伺いました。

- 野城 智也 氏
-
1985年東京大学大学院工学系研究科建築学科専攻博士課程修了、建設省建築研究所研究員、武蔵工業大学建築学科助教授、東京大学大学院工学系研究科助教授を経て2011年より現職。その間に、東京大学生産技術研究所所長(2009-2012)、東京大学副学長(2013-2015)を歴任。

サイバー・フィジカルシステム
私は建築・都市という場におけるCyber(情報)空間とPhysical(物理)空間、そして「人・社会集団」の3つの世界がつながり、人々に「豊益潤福(*)」をもたらす「サイバー・フィジカルシステム」を提唱しています。このシステムが円滑に機能するためには、3つの世界を関連付ける基盤となる仕組みが不可欠です。ここではその仕組みを「アーキテクチャ」と呼ぶことにします。
※豊(豊かさ)、益(便利さ)、潤(潤い)、福(幸福感)をあらわす野城先生が提唱する造語

アーキテクチャが実現すべき4原則
私はサイバー・フィジカルシステムのアーキテクチャには、実現すべき4つの原則があると考えています。原則1は「公正な恩恵の享受」です。我が国において、プラットフォームの運営者、サービサー、データのコレクターがすべて同じプレーヤーになるという形は適していないと考えています。また原則2として、参加・不参加の自由が重要だと思います。原則3は、自覚的選択の保証です。「IoTと関わらずにゆったり暮らしたい」という人生観を持つ人もいるからです。原則4は、創造に必要なデータ連携の容易性です。1+1を3にも4にもする価値を創造するには、Interoperability(相互連携運用性)が求められます。
Interoperabilityに関するいくつかの事例を紹介します。構造計画研究所のWi-Fi型スマートロック「RemoteLOCK」はガス湯沸かし器や電動窓と連動させることができます。それにより、玄関の開閉に合わせて、ガスコンロを消したり窓を開閉したりすることも可能です。また私も、緊急地震速報のデータと繋がることで地震発生の前にガスコンロを消す仕組み、スマートスピーカーからの音声コントロールでリクライニングベッドを操作する仕組みなどを作っています。Interoperabilityを高め、様々な機器やデータを連携することで、新しい価値を創造できる可能性は高まります。

中立的な立場で接続できるプラットフォーム
メーカーがユーザーを囲い込もうとするようなプラットフォームのあり方では、ユーザーの利益につながりにくく普及も進みません。かといって、機器が接続するたびにプロトコルを翻訳しなければならないというのも面倒です。そこで参考になるのはパソコンとプリンターの関係です。プリンターがどこのメーカーのものでも、OSが何であってもプリントできるのは、プリンタードライバーをパソコンにインストールしさえすればつなぐことができるからです。
私が提唱しているのは、「IoT-HUB」というプラットフォームです。このプラットフォームでは、Web APIとドライバーを組み合わせて接続します。機器メーカーはドライバーを作りさえすれば、外部のアプリケーションとつなぐことができます。
様々なメーカーの機器のアプリが同じ空間の中で走るようになると、「状況」に対して不都合なコマンドが発せられてしまう可能性が生じる等、対処すべき課題もあります。あるコンビニエンスストアの店舗で実験を行った際、「夏に空調機が十分に動かない」という奇妙な現象が起こりました。調べてみると、半オープン型の冷蔵庫に付いているセンサーが店舗全体を冷蔵庫と認識してフル稼働した結果、店舗内の温度が下がり空調機の働きが妨げられていました。「場所のコンテクスト」をとらえて店舗の全体最適を実現するロジックがなかったわけです。状況を認識し、最適な命令の組み合わせを実現していくことが大切であることを学びました。
中立的な立場で接続できるプラットフォームにおいて、相互接続環境が整うことによって、さまざまな企業が参入しやすくなるでしょう。オープンで公正な仕組みを作ることが、住宅・建築分野のloTの普及利用にとっても重要だと考えています。
社会連携研究部門の設置について
社会連携研究部門とは、公益性の高い共通の課題について、東京大学と民間機関等が共同して研究を実施することを目的として、東京大学内に研究部門を開設する制度です。当社が参画している社会連携研究部門「建築・都市サイバー・フィジカル・アーキテクチャ学」は以下の目的を掲げ、2020年4月にスタートしました。
1. 学際的なアプローチにより、Cyber空間とPhysical空間を整合・統合させるアーキテクチャを構想するとともに、その構築に資する学理を創成すること
2. アーキテクチャを利活用する応用研究を展開することにより、建築・都市において包括的なサービスが生まれ、サステナブルな建築・都市の実現に貢献していくこと

現在、当社から4名の所員がこの社会連携研究部門に参画し、野城先生との共同研究を進めております。本取り組みを通じて、サステナブルな建築・都市の実現に貢献してまいります。